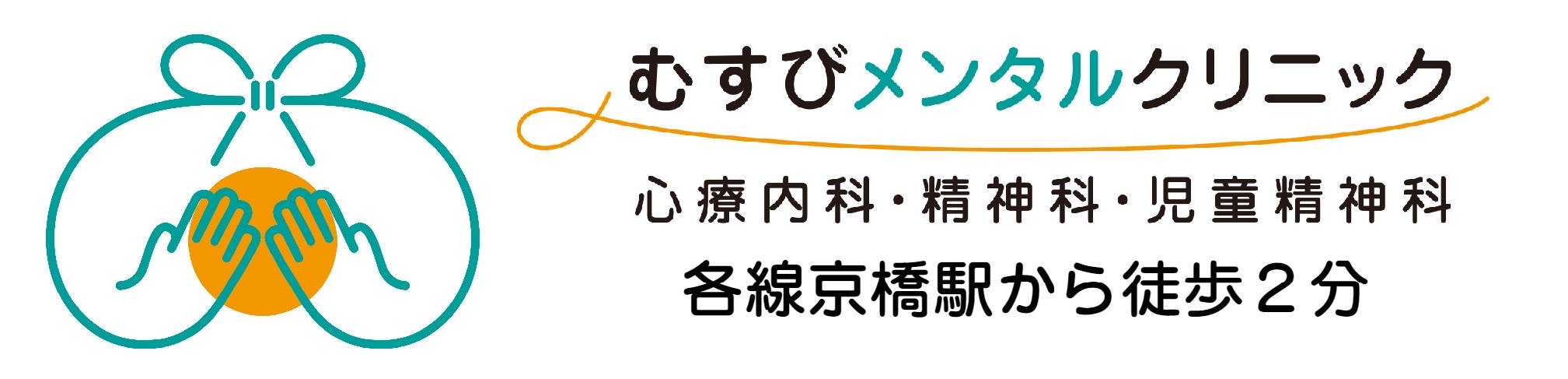「人と一緒にいると疲れてしまう」
「場の空気が読めないと言われる」
「なぜかうまくいかないことばかり」
そんなふうに、自分だけがどこかズレているような感覚を抱えていませんか?
理由ははっきりしないけれど、いつもどこかで「生きづらさ」を感じている。
それは、あなたの性格や努力の問題ではありません。
その"違和感"こそが、心からの大切なサインかもしれません。
こんなことに悩んで
いませんか?
- 友達づきあいや職場の人間関係がうまくいかない
- 空気を読むのが苦手で、あとから後悔することが多い
- 自分だけが「浮いている」ように感じる
- 感覚に敏感で、人混みや音、においに強いストレスを感じる
- 他人の何気ない言葉に傷つきやすい
- 「人と同じようにできない自分」がつらい
体に現れる主な症状
- 人と話すときに緊張しすぎて動悸がする
- 言葉が詰まりやすく、焦りを感じる
- 不安からくる胃痛や頭痛
- 社交の場を避けることで引きこもりがちになる
考えられる状態・特性
(鑑別疾患・背景)
自閉スペクトラム症(ASD)
空気を読む、曖昧な会話、雑談が苦手。
興味のあることに強く集中する反面、周囲と調和をとるのが難しい。
感覚の敏感さや「ルール」へのこだわりがあることも。
注意欠如・多動症(ADHD)
物事に集中するのが苦手、ミスや忘れ物が多い。
思いついたことをすぐ口にしてしまう。
「だらしない人」と誤解されやすく、自尊心が下がってしまうことも。
HSP(Highly Sensitive Person:非常に繊細な人)傾向
医学的に正式な診断名ではありませんが、感受性が強く刺激に敏感な方。
他人の表情や声のトーンにすぐ気づいて、気疲れしやすい。
生きづらさの背景として、こうした気質が関係することもあります。
発達性トラウマ・愛着の問題
幼少期の環境や関係性の中で、他者とのつながりに困難を抱えた経験がある場合。
自分の気持ちがわからない、人との距離感がつかめないなどの生きづらさにつながることがあります。
もしかしたら「名前」がつくかもしれません
「診断されるのが怖い」と思われるかもしれません。
でも、自分の感じていることに「名前」がつくことで、初めて自分を責めずにいられた。
そうおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
大切なのは、診断そのものではなく、「どうすれば生きやすくなるか」を一緒に考えていくことです。
当クリニックでできるサポート
あなたの話を丁寧に聞き、背景や特徴を一緒に見つけていきます。
必要に応じて心理検査や発達特性の評価も可能です。
生活の工夫、人間関係の築き方、感覚との付き合い方なども含めた支援をご提案します。
診断よりも「今のつらさに何ができるか」を大切にしています。
最後に
「周りに合わせられない自分が悪い」と思っていませんか?
実はあなたの中にある"違い"は、乗りこなし方を身につけると"強み"にもなります。
今の生きづらさを、少しでも軽くするためにあなたらしく生きられる方法を、私たちと一緒に探していきませんか?