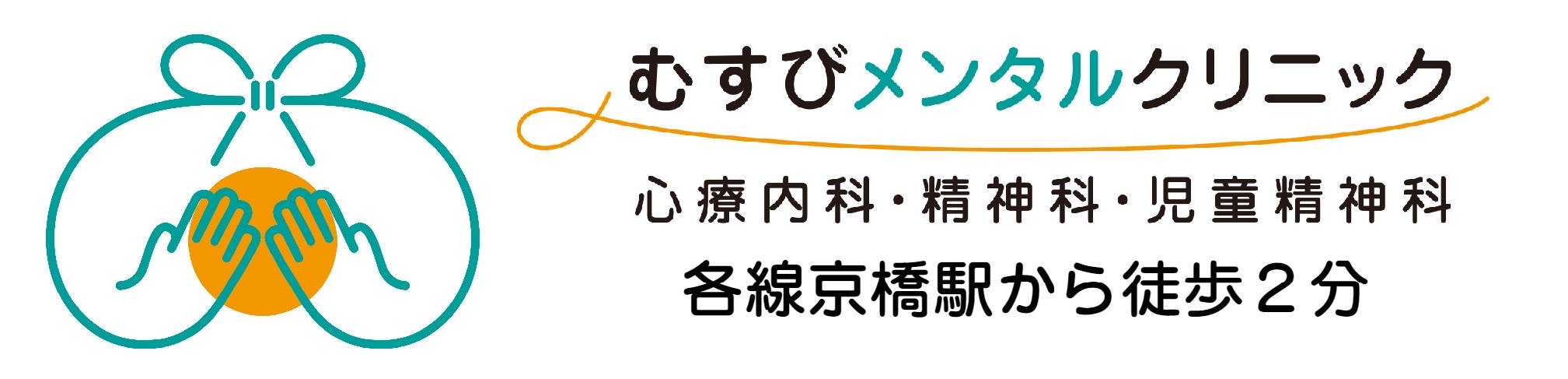気分が晴れない、理由もなく不安になる、気持ちの浮き沈みがつらい…。
心の不調は、目に見えないぶん、まわりにも伝えづらく、自分を責めてしまいがちです。
でも、あなたの感じていることには、ちゃんと意味があります。
どうかひとりで抱えず、まずはその心の声を聴かせてください。
「気分の落ち込み」「不安」「波」とは?
- 気分が沈んでやる気が出ない
- 先のことを考えると不安で眠れない
- すぐに気持ちが揺れてしまって疲れる
こうした心の変化は、誰にでも起こり得るものですが、つらさが続くと生活に支障が出てしまいます。
心に現れる主な症状
- 理由のわからない落ち込みが続く
- 漠然とした不安が消えない
- 何事にもやる気が起きない
- 集中力が低下する
- 自己否定的な考えが増える
- 些細なことで涙が出る
- 人との関わりを避けたくなる
体に現れる主な症状
- 不眠や睡眠の質の低下
- 食欲の変化(増加または減少)
- 疲労感が抜けない
- 頭痛や肩こりがひどい
- 胃の不調や吐き気
- 動悸や息苦しさ
- 手足の震えや冷え
考えられる病気や状態
うつ病
気分がずっと沈んで、何をしても楽しく感じられない。
食欲・睡眠の変化、疲れやすさ、集中力の低下。
不安障害(全般性不安症、パニック症、社交不安症など)
常に「何か悪いことが起きそう」と感じてしまい、胸がドキドキしたり、息苦しくなることがあり。
人前に出ることが怖い、緊張で体に症状が出る。
気分変調症
比較的軽い気分の落ち込みが、何年も続いている。
「昔からずっとやる気が出ない」「性格のせいかな」と感じている。
双極性障害(躁うつ病)
落ち込む時期と、逆に気分が高まってハイになる時期がある。
ハイな時は寝なくても平気になったり、しゃべり続けたりする。
自分では「波」に気づきにくいこともある。
月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)
生理前になると強いイライラ、不安、落ち込みが出る。
繰り返す気分の波に、自分でも戸惑ってしまう。
自分を責める前に…
「気の持ちよう」と言われたり、「こんなことで弱っていてはダメ」と思ってしまう方も少なくありません。
でも、心の不調は意志の弱さではなく、脳や体のバランスの問題であることも多いのです。
あなたのつらさには、必ず理由があります。
当クリニックでできる
サポート
- 気分や体調の変化を丁寧にうかがいます。
- 体の病気が隠れているせいで気分の波に繋がっている場合もあります。必要に応じて血液検査や心理検査などを行い、原因を一緒に探します。
- お薬やカウンセリング、生活面のアドバイスなど、あなたに合った方法をご提案します。
- 「こうなりたい」「こう過ごしたい」というお気持ちを大切にします。
最後に
あなたの心に波があるのは、弱さではありません。
その波と上手につきあっていく方法を、一緒に探していきましょう。