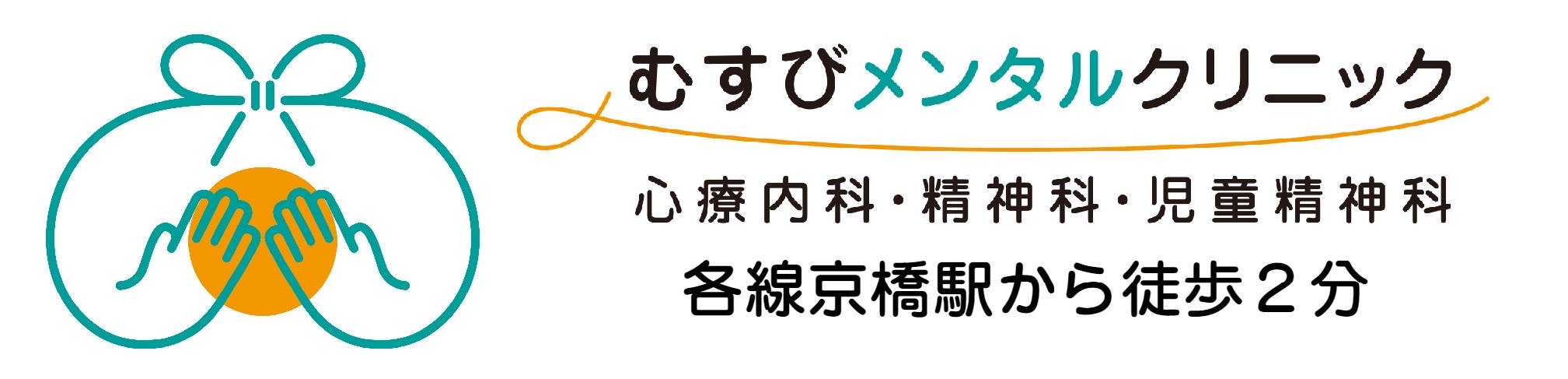どう考えても後悔するとわかっているのに、また同じ行動をしてしまう。
「やめたい」と思っているのに、やめられない。
「自分はダメな人間なんだ」と責めてしまう。
こうした悩みは、とても深く、言葉にしにくいものです。
けれどそこには、あなたが必死にバランスを取ろうとしてきた心の背景があるのかもしれません。
「わかっているのにやめられない」は、あなたのせいではありません。
こんなことに心当たりはありませんか?
- 夜中につい過食してしまう/衝動的に買い物をしてしまう
- 人間関係でいつも同じパターンで後悔してしまう
- 怒らないと決めたのに、また強く言いすぎてしまった
- SNSでの投稿・検索・確認をやめられない
- ギャンブルや性的な行動を繰り返してしまう
- リストカットや自傷行為を「ダメだとわかっていても」してしまう
考えられる状態や背景
(鑑別診断)
強迫性障害・衝動制御の障害
本人の意志とは関係なく、繰り返し行動せずにいられない。
不安や違和感を打ち消すための「儀式」的行動として出てくることも。
愛着の問題/発達性トラウマ・複雑性PTSD
幼少期の人間関係で安心感を育みにくかった場合。
「わかっていても止められない」行動パターンが防衛反応として根づいていることがあります。
ADHDやASDなどの発達特性
衝動性の強さ、感覚の偏り、こだわりなどから同じ行動が繰り返される。
「ダメだとわかっていても、その瞬間に我慢が効かない」ことが多い。
うつ病・不安障害などの二次的な影響
ストレスに対処する手段が少ないとき、「わかっているけど繰り返してしまう」行動で自分を保っている場合もあります。
なぜ「やめたいのにやめられない」のか?
多くの場合、それは「悪いクセ」ではなく、"心の痛み"から自分を守るための手段として繰り返されている行動です。
つまり、その行動には「意味」があるのです。
まずは自分を責めることから少し距離を取り、どうしてそうなるのか・どうすればラクになるのかを一緒に考えていくことが、大切な第一歩です。
当クリニックでできる
サポート
- 「繰り返してしまう行動」の背景にある気持ちや経験を丁寧にうかがいます
- 発達特性や愛着の傾向、トラウマの影響など、必要に応じて心理検査も含めて整理します
- カウンセリング、感情調整の練習、行動の切り替え方などの支援を行います
- ご希望に応じて、お薬や診断書、福祉的支援も含めたご提案も可能です
「診断名をつけて終わり」ではなく、「どうすればよくなるか」に焦点を当てています
最後に
くり返してしまう行動があることは、あなたがつらさを抱えながらも、何とか毎日を生きている証です。
その奥にある感情や、守りたかったものに、私たちはそっと寄り添います。
「同じことをくり返す自分」ではなく、「本当はどうしたかったのか」に目を向けることで、
日々が少しずつ変わっていくことがあります。
どうか一人で責めずに、ご相談ください。
ここは、あなたが安心して本音を話せる場所でありたいと願っています。