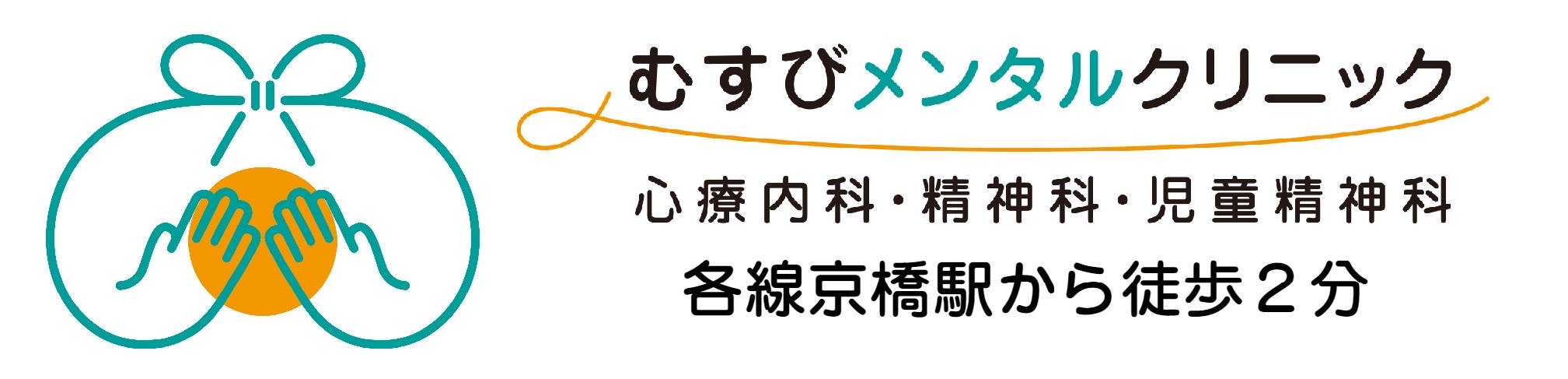気づくと部屋が散らかっている。
忘れ物、遅刻、締切の遅れが続く。
「今度こそちゃんとしよう」と思っているのに、またできなかった。
そんな日々に、落ち込んだり、自信をなくしていませんか?
でも、それはあなたの"意志の弱さ"や"努力不足"のせいではないかもしれません。
大人になってから気づく「発達特性」が、関係していることがあります。
よくあるお悩みの例
- 片付けや整理整頓ができず、常に物を探している
- 時間の見通しが立てられず、いつもギリギリになってしまう
- 締切や約束を守れず、職場で信頼を失いかけている
- 複数のことを並行して進められない
- 大事な予定を忘れてしまう/忘れたことに気づかない
- 「やる気はあるのに、なぜかできない」という苦しさ
考えられる状態・特性
(鑑別診断)
注意欠如・多動症(ADHD)〔成人型〕
- 不注意(忘れっぽい、集中が続かない)
- 衝動性(思いつきで行動してしまう)
- 多動(落ち着かない感覚、思考が飛びやすい)
- 子ども時代に気づかれず、大人になってから困難が顕在化するケースも多くあります。
自閉スペクトラム症(ASD)
特定のことには強く集中できるが、日常の柔軟な対応が苦手。
段取り・優先順位づけが難しく、「何から手をつけたらいいかわからない」状態になりやすい。
うつ病・適応障害などの気分の障害
疲れやすく、やる気が出ない。
頭ではわかっていても、体が動かない。
発達特性が背景にあり、二次的に抑うつ状態を引き起こすこともあります。
パーソナリティ傾向/慢性的なストレス反応
完璧主義や「失敗してはいけない」という強い思い込みから、始められない・終わらせられない。
他人との比較や自己否定のクセが、行動を妨げてしまう。
「発達障害」=「病気」ではありません
発達の特性とは、「できること」「苦手なこと」のバランスの違いです。
うまくいかないのは、「あなたが悪い」からではなく、環境や方法が合っていないだけかもしれません。
苦手な部分には「工夫」や「支援」を。
得意な部分には「活かし方」を。
それが見つかれば、毎日は少しずつラクになります。
当クリニックでできる
サポート
- 日常生活で困っていることを丁寧にお聞きし、背景にある特性や状態を整理していきます。
- 必要に応じて、心理検査(WAISなど)や発達評価を行い、特性の全体像を把握します。
- 「診断ありき」ではなく、あくまで困りごとの解決を目的に関わります。
- ご希望に応じて、お薬・環境調整・カウンセリングなどの選択肢をご提案します。
- ご家族や職場への説明が必要な場合は、診断書の作成や情報提供も可能です。
最後に
片付けられない、遅刻してしまう、物事がうまく回らない。
そんな毎日がつらくても、それは「あなたがダメだから」ではありません。
「どうしたらもっと自分らしく暮らせるか」
それを一緒に考えていくことが、私たちの役割です。