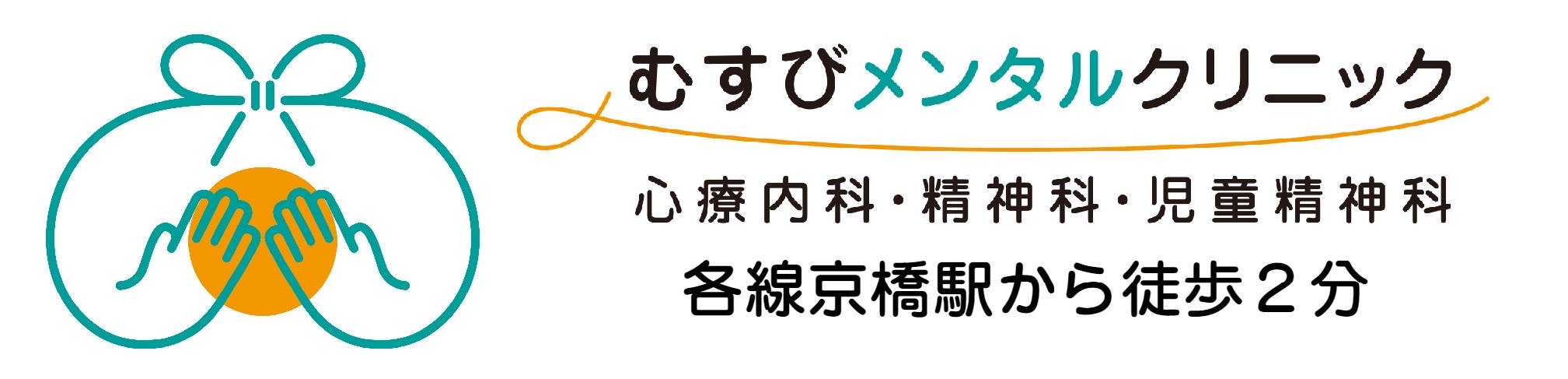「疲れているのに眠れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」
そんな夜が続くと、体だけでなく心までつらくなってきますよね。
睡眠は心と体の回復にとってとても大切な時間です。
その"眠れなさ"には、ちゃんとした理由があるかもしれません。
どんな睡眠の悩みが
ありますか?
眠れないといっても、いろいろなタイプがあります。
ご自身の状態に当てはまるものがあるか、参考にしてみてください。
入眠困難:布団に入ってもなかなか眠れない(30分〜1時間以上)
中途覚醒:夜中に何度も目が覚めてしまう
早朝覚醒:朝早く目が覚めて、そこから眠れない
熟眠感の欠如:一応眠っているはずなのに、疲れが取れていない感じがする
考えられる病気や状態
不眠症(いわゆる「睡眠障害」)
入眠・中途覚醒・早朝覚醒のいずれかが続く。
日中の眠気、集中力の低下、イライラなどを引き起こす。
ストレス、生活リズムの乱れ、加齢などが原因になることも。
うつ病
寝つきが悪くなる、夜中や早朝に目が覚める。
起きたときから気分が重い。
睡眠の質の低下が最初のサインになることも。
不安障害
心配ごとが頭から離れず、眠れない。
眠りに入っても、ふとした不安で目が覚めてしまう。
「眠らなきゃ」というプレッシャーがかえって眠りを妨げる。
睡眠時無呼吸症候群
いびきが大きい、睡眠中に呼吸が止まる。
朝起きてもだるい、日中に強い眠気がある。
ご自身では気づかないことも多く、ご家族が指摘する場合も。
アルコール・カフェインの影響、生活習慣の乱れ
「寝酒」がかえって眠りを浅くしてしまう。その飲酒量の増加はアルコール依存の入口かもしれません。
夜遅くのスマホ使用、昼夜逆転生活なども睡眠に影響します。
一度、ご相談ください
「寝られないだけで病院に行ってもいいの?」と思われる方もいるかもしれません。
でも、睡眠の不調は心と体の健康を守るための大切なサインです。
改善できる方法があります。一緒に取り組んでいきましょう。
当クリニックでできる
サポート
- 睡眠の状態を丁寧にうかがい、背景にある原因を一緒に探します。
- 体の病気が隠れているせいで不眠に繋がっている場合もあります。必要に応じて血液検査や心理検査などを行い、原因を一緒に探します。
- 状況に応じて、薬物治療・非薬物療法(睡眠衛生指導や生活リズム調整)などをご提案します。
「眠ることが怖い」「眠れない自分が嫌だ」そんな気持ちにも寄り添います
最後に
あなたの"眠れなさ"には、必ず理由があります。
安心して眠れる夜を、もう一度取り戻すためのお手伝いをさせてください。