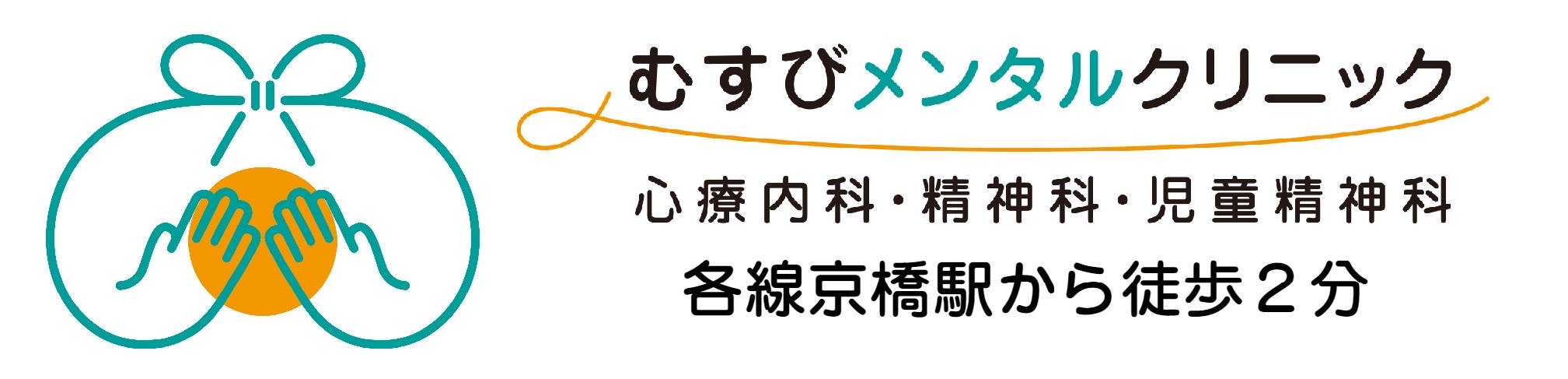「落ち着きがない」「こだわりが強い」「集団が苦手みたい」そんなふうに、お子さんの様子が周りの子と少し違って見えて、なんとなく気になっている。
でも、「気にしすぎかもしれない」「親のせいなのかも」と自分を責めてしまったり、 相談すること自体にためらいを感じる方も多いのではないでしょうか。
まずお伝えしたいのは、その"気づき"は、子どもを大切に想う気持ちがあるからこそ生まれたものだということ。
「ちょっと気になる」という段階からでも、どうぞ安心してご相談ください。
こんな様子が気になっていませんか?
- 名前を呼んでも反応が薄い
- 落ち着きがなく、目を離せない
- 特定の物・ルール・順番へのこだわりが強い
- 人とのやりとりがぎこちない/視線が合いにくい
- 感覚の敏感さ(音、におい、肌ざわりなど)
- 集団行動や初めての場所が極端に苦手
- 一方的なおしゃべりが多い、空気が読みにくい
- 気になる行動がある一方で、すごく得意なこともある
- もちろん、これらの特徴が「必ずしも発達の問題を示している」とは限りません。
考えられる状態や特性
自閉スペクトラム症(ASD)
コミュニケーションのスタイルや興味のもち方に独特な傾向。
感覚の過敏さ・不器用さ・こだわりなども。
注意欠如・多動症(ADHD)
落ち着きがない、忘れ物が多い、衝動的に行動してしまう。
集中力にムラがあり、「できる時とできない時」がある。
知的発達の遅れや学習面でのつまずき
言葉の発達がゆっくり。
数や文字の理解がうまくいかないことがある。
グレーゾーンの発達特性
はっきりと診断には当てはまらないけれど、「ちょっと特性がある」とされる子どもたちもいます。
配慮や支援の有無で、学校生活や人間関係に大きな違いが出ることもあります。
早期に気づくことで、できる支援があります
子どもは「育てやすさ」に個人差があって当然です。
でも、もしも発達の特性が関係している場合には、その子に合った関わり方や支援の方法があります。
そのひとつが「療育」と呼ばれる支援です。
「療育」ってなんだろう?
「療育」とは、子ども一人ひとりの特性に合わせて、 社会性・コミュニケーション・生活スキルなどを育てていく支援のことです。
- 小さな「できた!」を積み重ねていくこと
- 苦手なことは「工夫して乗り越える力」を育てること
- ご家庭や園・学校と連携し、安心できる環境を整えること
決して"特別"なものではなく、その子がその子らしく成長するための手助けとして、多くのお子さんが活用しています。
「療育を受ける=何かが劣っている」ということでは、決してありません。
当クリニックでできる
サポート
- お子さんの様子を丁寧におうかがいし、特性や背景を一緒に整理していきます
- 必要に応じて心理検査(WISC、PARSなど)を行い、得意・苦手の傾向を把握します
- 療育機関や支援センターのご紹介・連携も可能です
- ご家庭での接し方の工夫、園・学校とのコミュニケーションについてのご相談も承ります
- 診断を急がず、「いま何が必要か」を一緒に考えます
最後に
お子さんのことで悩んだり、不安を抱えることは、「よい親じゃないから」ではなく、「真剣に向き合っている証拠」です。
ちょっとした違和感から始まることもあります。
ひとりで悩まず、「この子らしさ」を大切にするための一歩として、私たちにご相談ください。
安心して話せる場所でありたいと、心から願っています。