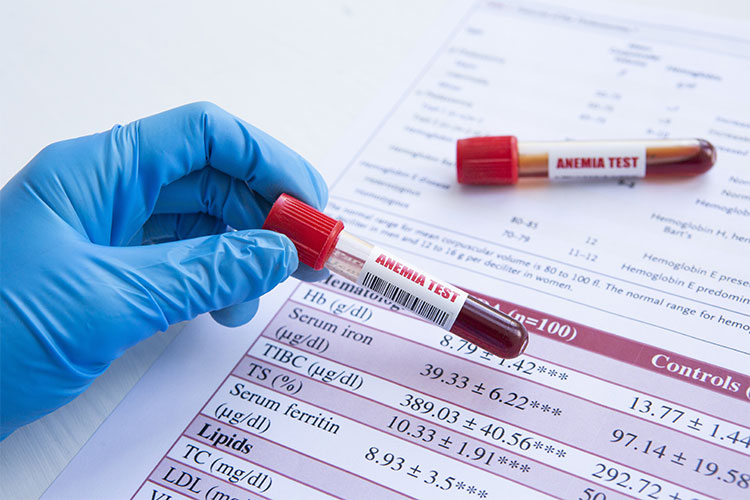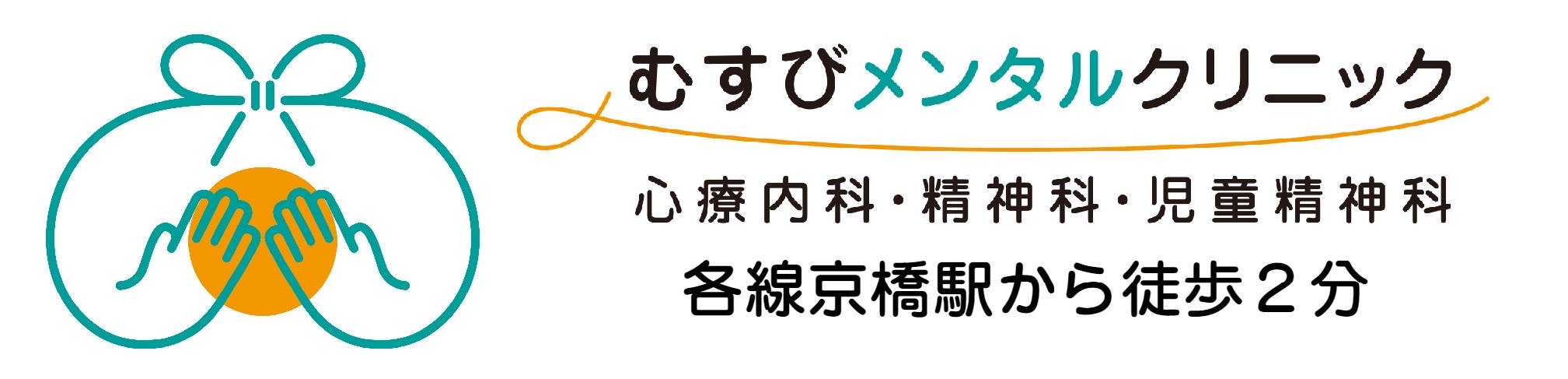血液検査について
採血でわかる、こころの不調の背景、こころとからだは深くつながっています。
精神症状があるとき、その背景に身体的な原因が隠れていることがあります。
採血で見つかることがある代表的な例
| 可能性のある身体疾患 | 主な症状 | 採血でわかる項目例 |
|---|---|---|
| 甲状腺機能の異常(バセドウ病・橋本病など) | イライラ・不安・抑うつ・無気力 | TSH, FT3, FT4 |
| 電解質の異常(低ナトリウム・低カリウムなど) | 倦怠感・混乱・集中力低下 | Na, K など |
| 貧血(鉄欠乏性など) | 疲れやすい・抑うつ気分・集中困難 | Hb, Fe, フェリチンなど |
| ビタミン不足(B12・葉酸など) | 抑うつ・意欲低下・物忘れ | Vit B12, 葉酸 |
| 肝機能や腎機能の異常 | 意識のかすみ・だるさ・不安定な気分 | AST, ALT, Cr, BUN など |
こうした異常があると、気分の波や集中力の低下、不安感や無気力感といった症状が出ることがあり、精神疾患と区別がつきにくくなることもあります。
採血を行う目的は「安心のため」
採血は、あなたのこころの症状が、どこから来ているのかを一緒に見つけるための大切な手段のひとつです。
「身体は元気です」と安心できる材料にもなりますし、もし何か異常があっても、早めに気づいて対処することができます。
お薬を使う場合にも、ときどき体を確認しましょう
治療でお薬を使う場合は、その薬が体に合っているかどうかを見るためにも、採血が役立ちます。
たとえば、抗精神病薬・気分安定薬・睡眠薬などの一部は、肝臓・腎臓・血糖・脂質・ホルモンバランスなどに影響を与えることがあります。でもご安心ください。
採血の頻度は年に1〜2回程度が一般的で、必要以上に何度も行うことはありません。
ご希望や体調に応じて、無理のない範囲で相談しながら進めていきます。
漢方薬を飲む場合も、体の変化を確認することがあります
「漢方なら安心」と思われがちですが、実は漢方にも体に影響を与える成分が含まれています。
たとえば
- 柴胡(さいこ)を含む処方:肝機能に影響を与えることがある
- 甘草(かんぞう)を含む処方:低カリウム血症のリスクがある
漢方薬を安全に、安心して飲み続けるためにも、ときどきの採血で身体の状態をチェックしておくことがとても大切です。
最後に
採血は、「薬のため」でも「病気を疑っているから」でもありません。
これはあなた自身の体とこころを守るための、大切な情報のひとつです。
疑問や不安があるときには、どうぞ遠慮なくおたずねください。
あなたが安心して治療を続けられるよう、私たちはていねいにご説明しながら進めていきます。
心理検査について
「なぜ検査が必要なの?」「検査の結果で何かが決まってしまうの?」
そんな不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
でも私たちが心理検査をおすすめするのは、困りごとの背景を理解し、あなたに合った過ごし方・支援のヒントを一緒に見つけるためです。
心理検査は、「診断のため」だけではなく「どんな力があるのか」「どこでつまずきやすいのか」そして「どんな環境ならその人らしく過ごせるか」をていねいに探る手段でもあります。
心理検査でわかること
心理検査にはさまざまな種類があり、目的に応じて使い分けます。主に以下のようなことがわかります。
- 得意/不得意の傾向を整理し、自己理解や進路選び・職場環境の検討に役立てる
- 困りごとの原因や背景にある発達的な特性・感情の傾向を探る
- どんな支援や配慮があると、学校や職場でより過ごしやすくなるかを考える
- 医師による診断や、福祉・教育の支援制度の利用判断の参考にする
主な検査のご紹介
WAIS(ウェイス)/WISC(ウィスク)【知能検査】
WAISは成人向け、WISCは児童向けの知能検査です。
「IQ」だけではなく、情報処理の方法、集中力、言語能力、処理スピードなどの"認知のプロファイル"を明らかにします。
活用できる場面
得意な作業スタイルや、苦手な課題への対応方法を見つけ、「どうして仕事や勉強がうまくいかないのか」が整理され、必要な配慮がわかる。
障害者雇用や就労移行支援の利用時にも、適切な支援計画につながります。
PARS(発達障害診断支援ツール)
自閉スペクトラム症(ASD)の傾向を、ご本人やご家族への聞き取りを通して評価します。
幼少期からの様子を丁寧にふりかえり、特性の有無や強さを確認します。
特徴
「なぜ人間関係で疲れやすいのか」「こだわりや不安は特性と関係があるのか」といった疑問に答えるヒントになります。
診断が目的ではなく、理解と支援につなげるための"見取り図"として活用されます。
MSPA(多面的評価シート)
発達障害を持つ方の生活全体のつまずきや強みを"支援のために"整理するシート型のアセスメントツールです。医師・心理士・支援者などが協力し、就労・学習・日常生活での配慮点を言語化するために用いられます
特徴
「どんな場面で、どんなサポートがあると力が発揮できるか」を具体的に把握できます。
支援学校や職場の配慮依頼書、福祉サービス利用の際の情報共有にも役立ちます。
よくあるご相談
- 「適職や進路の参考になりますか?」
- はい。強みや注意点が整理されることで、「自分に合う仕事のスタイル」や「向いている環境」が見えやすくなります
- 「職場や学校に伝える資料になりますか?」
- 必要に応じて、検査結果を活用した配慮依頼書の作成や意見書のご相談も承っています
- 「検査を受けたからといって、診断されるわけではないですか?」
- 検査はあくまで"情報のひとつ"です。診断が必要な場合も、ご本人の希望を尊重しながら判断します
- 「料金はどのくらいですか?」
- 一部検査は自費となりますが、最も高額な検査でも施行、結果のフィードバックを含め多くの方が5,000円程度でご利用になれます(2025年5月時点)。予約状況によって適宜料金体系の見直しを行ってまいりますので最新の料金体系についてはお問い合わせください。
最後に
心理検査は、あなた自身やお子さんの「らしさ」を見つけるための大切な手がかりです。
苦手なことは"工夫すべきポイント"として、得意なことは"活かせる武器"として、
一緒に整理し、日々をより自分らしく過ごすためのヒントを探していきましょう。