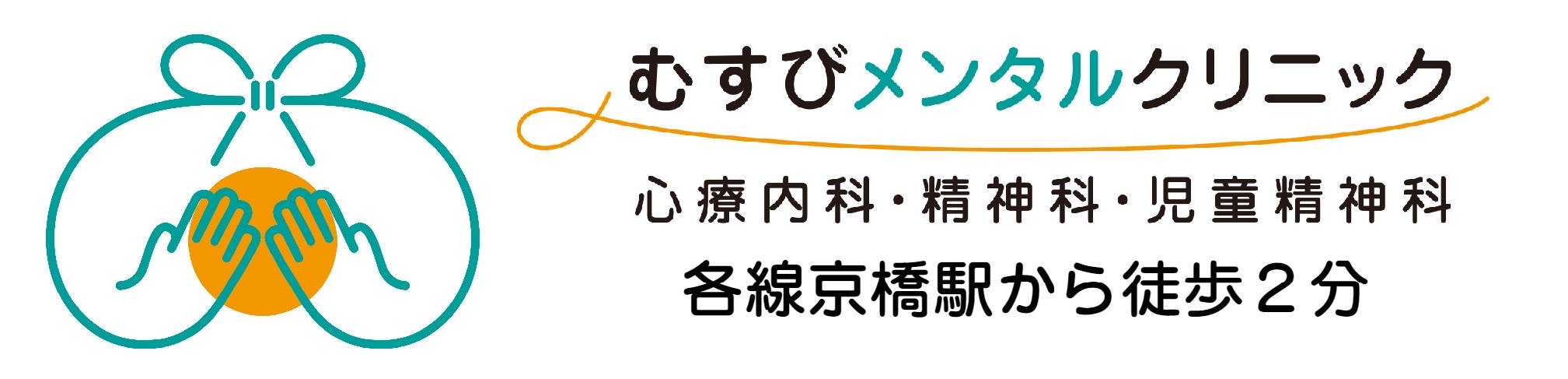「朝になると体が重くなる」「行かなきゃいけないのに動けない」
そんな気持ちをひとりで抱えていませんか?
無理にがんばらなくて大丈夫。まずは、その気持ちに耳を傾けてみましょう。
どうして「行きたくない」と感じるの?
心や体が「つかれているよ」とサインを出していることがあります
人間関係、仕事・学業のプレッシャー、生活リズムの乱れなど、さまざまな要因が重なって「行けない」と感じることがあります
心に現れる主な症状
- イライラや落ち着きのなさが続く
- 気分が沈んで何もする気が起きない
- 仕事や学業に集中できない
- 些細なことで不安になる
- 周囲の目が気になって仕方がない
- 自分を責めてしまう気持ちが強くなる
- 人との交流を避けたくなる
- 将来に対して希望が持てない
体に現れる主な症状
- 疲れやすく、だるさが続く
- 頭痛や肩こりがひどくなる
- 胃の痛みや食欲不振
- 吐き気や胃部不快感
- 睡眠障害(不眠や過眠)
- 動悸や息苦しさ
- 手足の震えや冷え
- 急な体重の増減
考えられる状態や病気
以下のような状態が背景にあることがあります。もちろん、診断は慎重に行いますが、目安としてご紹介します。
うつ病・抑うつ状態
気分が強く落ち込み、特に朝に起きられない。
興味がなくなる。
疲れやすくなるなどの症状が続きます。
適応障害
特定の環境(職場や学校など)で強いストレスを感じ、不安や落ち込みが出る状態です。休日などには症状が軽くなる傾向があります。
不安障害(社交不安症・全般性不安症など)
人前で話す、他人と接することに強い不安や恐怖を感じ、常に「失敗したらどうしよう」と不安にとらわれてしまう。
自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如多動症(ADHD)
職場や学校での人間関係やコミュニケーションが極端に負担、環境の変化や決まりごとにうまく適応できず疲弊してしまう。
発達性トラウマや過去のつらい経験による影響
「何かをきっかけに行けなくなった」背景に、過去のトラウマがあることもあります。
こんなときこそ、
ご相談ください
「病気なのかどうかもわからない…」
そんなときこそ、私たちにご相談ください。
必要なときは診断や治療も行いますが、まずは“今の気持ち”を整理するお手伝いをさせてください。
当クリニックでできる
サポート
- 医師によるていねいな面談と診察。
- 必要に応じた診断と治療。(お薬は無理におすすめしません。漢方薬での治療も可能です)
- 心理士とのカウンセリング。(希望に応じて)
- 職場・学校との調整支援。(診断書の作成、相談対応)
- 漢方による治療も可能です。
最後に
行けない自分を責めないでください。
「つらい」と感じるその心に、私たちは真剣に向き合います。